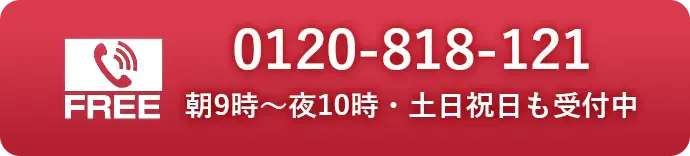- 任意整理を弁護士に依頼した場合に,和解による債権者への返済はいつ頃から始まりますか?
-
任意整理を弁護士に依頼すると,受任通知を各債権者(貸金業者)へ発送しますので,返済・取立が一時的に止まります。その後,各債権者から開示された取引履歴(借入・返済の日時や金額,残高などが記載された書類)に基づいて,利息制限法の法定利率まで引き直した再計算を行います。これによって,法律に則った正しい残りの債務の金額を確認していきます(債権調査)。この調査が終了する目安は,ご依頼を受けてからおよそ2~3ヵ月後となります。
債権調査が終了した後,当事務所とご依頼者様とで具体的な返済方法や返済計画を話し合って決めます。そして,その返済計画に沿った形で各債権者との和解交渉が始まります。
なお,当事務所では,和解交渉の前に月々の返済に必要な分割金の2ヵ月分をプールすることを推奨しています。これは,和解した後に3年間(36回),場合によっては5年間(60回)の返済計画の中で,予定外の大きな出費によって返済ができなくなってしまった場合などにおいても,毎月の返済を滞らせないためのものです。
ですから,和解による債権者への返済は,債権調査→プール金の積み立て→返済計画の話し合い→分割返済の和解交渉という流れを経て,おおむねご依頼を受けてから,半年後(6ヵ月後)には開始することになるのが一般的です。
- 返還された過払い金に税金はかかりますか?
-
返還された過払い金に税金がかかるどうかは、返還を受けたその人が借入先に支払った利息を必要経費として確定申告していたかどうかによって決まります。
普通にお勤めされている人などであれば、借入先に支払った利息を必要経費として確定申告することはないと思いますから、そのような場合には払い過ぎた利息である過払い金の返還を受けても税金がかかることはありません。一方、商売をしていたりして借入先に払った利息を必要経費として確定申告していた人は、当初経費として申告していたものが戻ってきたわけですから、返還を受けた年の収入として申告する必要があり税金がかかることになります。
なお、過払い金そのものだけではなく、返還までの利息も併せて回収できることがありますが、この利息は税金を計算するにあたって収入に含めて考えますから、税金がかかってくることになります。
- 一部の貸金業者だけ過払い金請求を依頼できますか?
-
任意整理は、裁判所を介さない手続なので、整理の対象とする貸金業者を任意に選択することが可能です。例えば金利が低い貸金業者は整理せず、一部の貸金業者のみを弁護士に依頼して過払い金の請求することも可能です。取引期間、約定金利、借金の残額等を勘案し、過払い金が発生している可能性がある貸金業者については、弁護士に依頼することをお勧めします。
- 取引履歴の開示請求に応じてもらえない場合はどのような対応が可能ですか?
-
貸金業者は取引履歴を開示する法的な義務を負っています。
しかし、取引履歴を廃棄したことを理由として、一部の取引履歴しか開示を行わない貸金業者も若干存在します。当事務所では、そのような貸金業者に対しては、何度も全部の取引履歴を開示するよう請求しますが、それでも開示を拒否する貸金業者が存在します。
そのような場合には、金融庁や各都道府県知事に行政指導を申告したり、訴訟を提起し、証拠保全や文書提出命令という手続で開示を求めることになります。
ただ、これらの裁判所の手続によっても開示に応じない貸金業者がいくつか存在し、現状の課題となっています。
もっとも、貸金業者からの協力を得られない場合には、資料をもとに取引経過を推定して計算し、過払い金を請求する方法や、初回の残高を無視し、0円として計算をするという方法で対応できる場合があります。
- 貸金業者は取引の履歴を素直に開示してくれるのですか?
-
以前は、貸金業者の取引履歴の開示義務を明確に定めた法律がなかったため、貸金業者の中には取引履歴の開示に応じなかったり、一部の取引履歴しか開示してこない貸金業者も多数存在しました。しかし、2005年7月19日、最高裁判所は、貸金業者に取引履歴を開示する義務があることを初めて認めました。この最高裁判例を受けて、現在では、ほとんどの貸金業者が取引履歴を開示してくれるようになりました。
- 過払い金を請求するとブラックリストに登録されてしまい、カードは利用できなくなりますか?
-
俗にいう「ブラックリスト」そのものは存在しませんが、信用情報機関の保有する信用情報に、返済能力に関する情報(事故情報)が登録されることを、「ブラックリストに登録される」などと表現することがあります。
上記の事故情報は、債務整理(自己破産・民事再生・任意整理など)が行われたときや、返済の遅滞が生じたような場合に登録されます。
一方で、過払い金を請求すること自体は、返済能力と無関係であり、ただちに信用情報機関に情報が登録される原因とはなりません。
もっとも、名目上の残債務がある状況で過払い金請求を行う場合には、債務整理を行うとみなされ、事故情報が登録される可能性があります。
この場合、債務が消滅したことが確認された段階で事故情報は削除されます。
完済している状況で過払い金請求を行う場合は、事故情報が登録されることはありません。ただし、過払い金請求には知っておきたいデメリットが存在します。詳しくは、以下のページをご覧ください。
過払い金のデメリットを見る
- 契約書等をなくしましたが、過払い金を請求できますか?
-
過払い金が発生するためには、通常5~7年間以上取引を継続していることが必要となりますので、その間に契約書や取引明細書を紛失している場合が多く見受けられます。
そのような資料を紛失している場合でも、貸金業者は全取引履歴を開示する法的な義務がありますので、開示された取引履歴をもとに過払い金の返還を請求することは可能です。
ただ、取引期間が長期におよぶ場合や完済経験がある場合には、貸金業者から全部の取引履歴が開示されない場合もあります。
全取引履歴が開示されているかどうかをチェックするためにも、契約書等の資料が残っているほうが望ましいといえます。また、「一番最初に借入をした時期」は大変重要な事項になりますので、できる限り借入当時のことを思い出してください。
- 過払い金請求の訴訟を起こすリスクは何ですか?
-
貸金業者と任意の和解が成立せず、裁判所に訴訟を提起する場合でも、リスクは特にありません。
訴訟活動は、すべて弁護士が行いますので、原則として依頼者の方が裁判所に行く必要はありません。ただ、全取引履歴が開示されていない場合や計算方法・消滅時効等の争いがある場合、訴訟が長期化し、1年間程度訴訟が継続してしまい、過払い金の返還が遅れるケースがあります。ただし、過払い金請求には手続前に知っておきたいデメリットが存在します。詳しくは、以下のページをご覧ください。
過払い金のデメリットを見る
- 過去に完済した貸金業者がありますが、それでも過払い金は請求できますか?
-
すでに完済しているとしても、過払い金が発生している場合は当然返還を請求することが可能です。完済している場合、引き直し計算をする前の状態ですでに借金の残額が0円の状態ですので、約定金利が法定の上限金利を超える場合には、ほぼ確実に過払い金が発生していることになります。もっとも、過払い金の返還請求権は、法律上、10年間(※)の消滅時効にかかりますので、完済してから10年(※)を経過している場合は、返還の請求が困難となるケースもあるので注意が必要です。
※法改正により、2020年4月1日以降に完済した場合、時効は最終返済日から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)に変更となりました。
- 過払い金を請求するときに、以前に借換をしたことがある場合、借換前の取引はどうなりますか?
-
同一の貸金業者から借換をして借換前の借金を清算した場合には、借換前と借換後の取引を1つの取引として法定金利に基づき引き直し計算を行い、過払い金の金額を確定します。そのため、借換前の取引がある場合には、過払い金の金額が増加する可能性がありますので、弁護士に依頼する際には必ず一番最初の取引時期を申告すべきです。
まずはお気軽にご相談ください。
朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中
0120-818-121